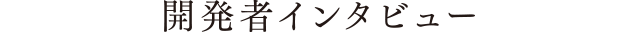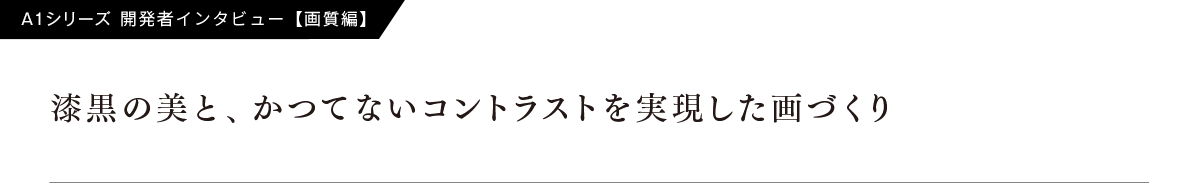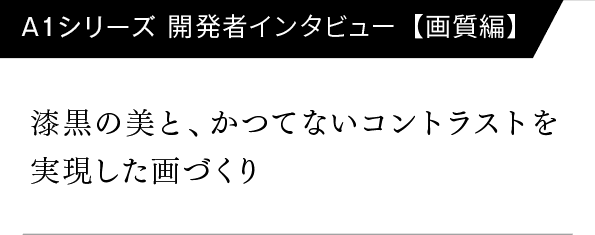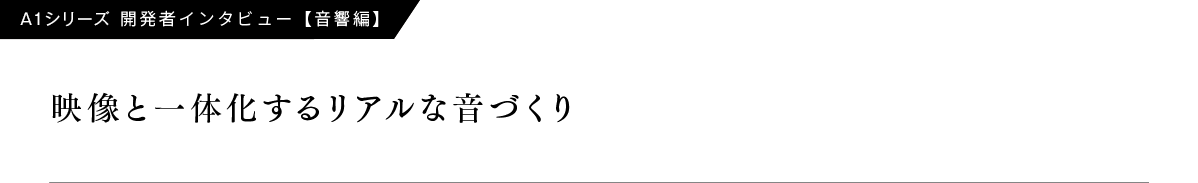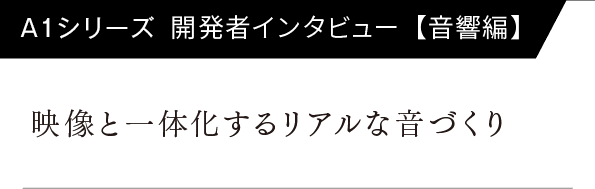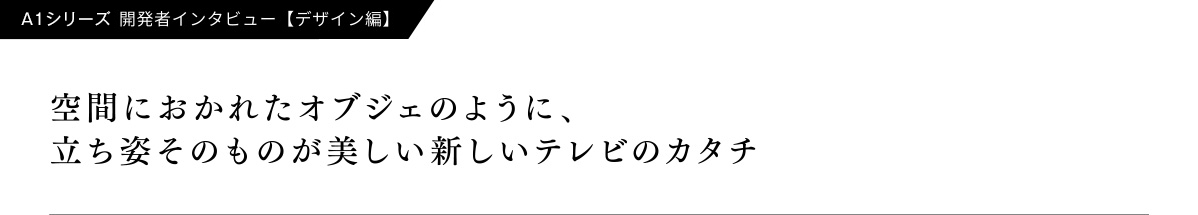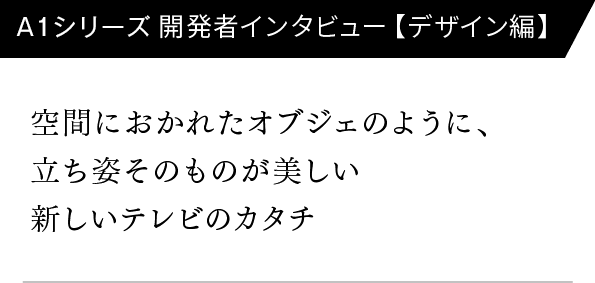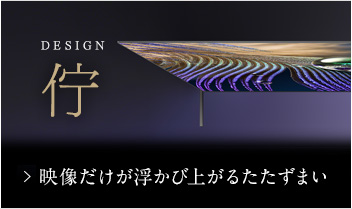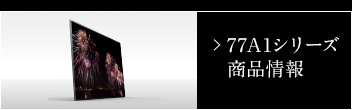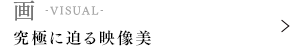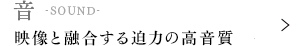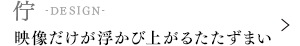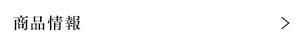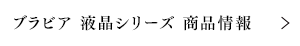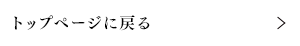「4K有機ELテレビ『A1シリーズ』の映像が誕生したプロセス」
―― いつ頃から有機ELパネルを使った新しいテレビの開発を検討していましたか?
<プロジェクトリーダー/画質設計 柴田>開発のたびに、パネルデバイスの選択肢に有機ELパネルがあったというのが事実です。これまでソニーは、液晶パネルや有機ELパネルなど、どのパネルデバイスに対しても最適な画作りができるように画質エンジンの開発を行ってきました。当然、2016年に発売したソニーのテレビ史上最高画質モデル『Z9Dシリーズ』に搭載している4K高画質プロセッサ−「X1 Extreme」を開発した時には、有機ELパネルに搭載することも視野にいれていました。
有機ELパネルの特性を理解して使いこなすには、すごく時間がかかります。理想的なパネルデバイスをきちんとつくり、そこに対して正しい表現のできる基礎となるシステムをつくり上げ、その上で画づくりをする必要があります。これらのプロセスを経ながら、ソニーが業務用モニターを含め長年の研究開発で培ってきた有機ELパネルのノウハウを存分に活用しました。そこに、「X1 Extreme」を組み合わせることで、有機ELパネルの能力を最大限に引き出せる『A1シリーズ』を完成させることができたという自負はあります。

「究極の没入体験を生み出す、引き込まれるような映像美」


―― 『A1シリーズ』の画質で特にこだわった点を教えてください
<柴田>有機ELパネルの特性上、星空や花火、夜の街並みのような黒の沈みとピクセル単位での輝きを求められるようなコントラスト表現は得意です。我々がこだわったのは、このコントラスト表現をさらに高めることと、なめらかな階調表現です。いわゆるプロの測定器の限界にまで辿り着くようなレベルでのパネル調整やその基礎的な画質設計を行い、超解像・HDRリマスター・Super Bit Mapping 4K HDRなどの技術を加えることで、例えば暗いシーンでも自然な奥行き感と、微妙な色のニュアンスをなめらかに再現し、物体の質感までをも描き出します。また、有機ELパネルの良さとして自発光なので色が濁らないという点もあります。色が濁らないということはそれだけ出せる色が多くなるということなので、トリルミナスディスプレイの広い色域を再現できます。
その結果、暗い映像で黒つぶれしがちな奥行き感や微妙な階調表現、色の違いもしっかりと表現することができ、引き込まれるような美しい映像を創出することができました。どんなコンテンツにもコントラストの違い、つまり光と影が共存します。たとえ明るいコンテンツでも陰影がしっかりつくことで立体感が生まれ、これまでと違った感覚でリアリティーのある映像に没入できます。
―― 映像だけに没入できるように工夫した点を教えてください
<チーフアートディレクター 田幸>画面周囲の要素を、極限まで減らすことを考えました。そのために、これまでのブラビアのデザインにおいて当たり前にやってきたことについても一から考え直しています。正面から見たときにスタンドがあり、スピーカーがある構造を採用しなかったのは大きな特長の1つですが、それ以外にも大きかったのはロゴの扱い方だと思います。
『SONY』のロゴは通常はパネル下部の中心部分に配置しているのですが、『A1シリーズ』に関しては、映像を引き立てるため究極のシンプルさを求めてロゴのサイズを小さくし、パネル下部の左端に配置しています。また、通常はパネル上部の左に配置している『BRAVIA』のロゴも、背面に移動しています。ロゴの扱い方はブランディングの観点からも非常に重要なので社内でもさまざまな議論はありましたが、すべては「究極の没入体験」という商品コンセプトを突き詰めた結果です。


「映像、音、デザインに携わる開発者が一致団結」
―― 『A1シリーズ』の開発の中で、思い出深いエピソードを教えてください

<柴田>開発のプロセスで私が一番感動した瞬間が、画面を震わせて音を出すというアイデアを具現化して、設計やデザイナー、そして商品企画など関係者全員が集まり初めてデモンストレーションを行った時に、「この方向性でいこう」と一致団結した瞬間でした。これならば新しい造形も生み出せるし、音としても成り立つ。そして何よりも商品コンセプトにしている「究極の没入体験」を実現できると、開発に携わっているすべてのメンバーが結束しました。その瞬間には鳥肌が立つぐらい感動しました。
自発光デバイスの有機ELパネルを活かすために設計した4K高画質プロセッサー「X1 Extreme」が、HDRや4Kなどの高解像度の映像はもちろん、放送を含むフルHD映像やネット動画などさまざまな映像をHDR化し、階調表現を高め、高精細に描きます。『A1シリーズ』なら、映画はもちろん、いつもご覧いただいている番組やコンテンツで、まるで現実世界を見ているかのようなリアリティー豊かな映像を楽しんでいただけると思います。

「画面から直接音が出ることこそ、リアルに最も近い状態」
―― 画面から音を出すテレビはどのような経緯で生まれたのですか?

<音響設計 吉岡>画面に映像が映り、その画面から直接音が出るというのが、テレビが理想としている状態であるといえます。そういうことができないかというのはエンジニアとしての夢でした。現実世界では、当然話している人から声が聞こえますよね?一般的なテレビでは、話している人の声がテレビの下部にあるスピーカーから出てくるので、脳が頑張って補正をしてくれるものの、それが小さなストレスになりリアル感も薄れがちです。テレビの画面の中で話している人の位置から声が出るというのが、一番ストレスのない状態でリアルに近い状態なのです。
このように映像と音は切っても切り離せません。多くの映画館では、スクリーンに無数の細かい穴が開いていて、背面のスピーカーから出る音を前方へ通すことで、映像と音が融合して一体となって聞こえます。『A1シリーズ』はこれと同様の「画面から音が出て、映像と重なって聞こえる」という体験を目指しました。実はエンジニアはブラウン管の時代から、画面自体から音を出す研究をしていましたが、前にスピーカーを置けば当然映像の一部が見えなくなります。また、画面を揺らすことで映像に影響が出るなど、いろいろな制約や制限があってこれまで実現することができませんでした。今回、有機ELパネルの特性を生かし、そこに画面を振動させて音を出すアクチュエーターを組み合わせることで実現できるのではないかという考えに至り、ソニーの過去の技術やノウハウも生かして、自信をもって商品として発売するところまでたどりつくことができました。

「画面を振動させて音を出すだけではなく、高音質を実現できるのは
オーディオメーカーとして培ったソニーの音響技術のなせる技」

―― スピーカーの役割について詳しく教えてください
<吉岡>テレビの背面にアクチュエーターを左右2つずつの計4つを配置し、背面のスタンドにサブウーファー1つを配置しています。アクチュエーターを使って単純に画面の左と右を振動させると、片方で鳴らした音がもう一方まで伝わってしまって、音がぶつかったり反射したりして音が悪くなってしまいますが、1枚のパネルの左と右でちゃんとチャンネルに分かれるように、内部は特殊な構造になっています。
主に中音〜高音を担当するアクチュエーターの配置場所は何度もシミュレーションを行って、加振点としてどこが最適なのかを見出しました。位置を変えただけで、音はガラッと変わってしまうのです。デザイナーにも何度も音のデモに足を運んでもらったことで見た目にも美しい位置にアクチュエーターを配置しつつ、どこから音が出ているか分かる、定位の良い音を創出できるポイントを見つけることができました。一方で、低音を担当するサブウーファーで迫力のある音を出そうとすると、容量を確保するためにどうしても大きなスペースが必要になりますし、さらには大きな振動が生じてしまいます。サブウーファーを単純にパネルと一体化させると、パネルが分厚くなりますし、振動が映像に影響を及ぼしてしまうのです。そこで、デザイナーや画質設計と相談し、サブウーファーは背面のスタンドに収納することでパネルを薄く保ちながら、映像視聴や画面の耐久性に影響が出ないように設計しました。

―― アクチュエーターを採用するにあたって苦労したことはありますか?

<吉岡>画面をアクチュエーターで振動させて音を出していますが、画面は硬くて重たいものなので、ただ画面にアクチュエーターを付けただけの音質だと小さいラジオのスピーカーよりも劣ってしまいます。音質を良くするためのハードルは高いものがありましたが、過去に発売したガラス管を加振して音を出す「サウンティーナ『NSA-PF1』」の音の解析技術や、音の再現性を高める平面スピーカーの開発ノウハウなどを結集して、周波数特性、残響などさまざまな音の特性を改善することができました。
<画質設計 柴田>画質設計として、画面を震わせながらも映像視聴や画面の耐久性には影響が出ないようにしてほしいなど、かなりこだわったリクエストをたくさん出しましたが、音響設計がありとあらゆる試行錯誤をしてくれて、その結果、すべての課題をクリアしてくれました。それ以外にもそれぞれの担当者の間で意見が分かれることもありましたが、議論を通して最終的には同じ方向を向き、ソニーだからこそ「究極の没入体験」ができる『A1シリーズ』を開発できたと思っています。

「映画館のような体験が家庭で味わえる」

―― どんなコンテンツを見るのがおすすめですか?
<吉岡>繰り返しになりますが、一番自然な状態で聞こえるので、まさに映画館のような「映像と音が重なって聞こえる」体験が家庭で味わえます。肝心の音質も、アクチュエーターとサブウーファー、さらに高度なデジタル音声信号処理回路を組み合わせて高音質を実現しているので、好きな番組をご覧になればそのリアルさをすぐにわかっていただけると思います。たとえば、映画や音楽番組などの低音から高音までバラエティー豊かな音の出るコンテンツであれば、そのリアルな音とともに興奮や空気感までも感じられるので、映画の世界やコンサート会場にいるような感覚で目の前に「感動」が広がってくることと思います。

「没入感を実現する佇まいへの妥協なきこだわり」
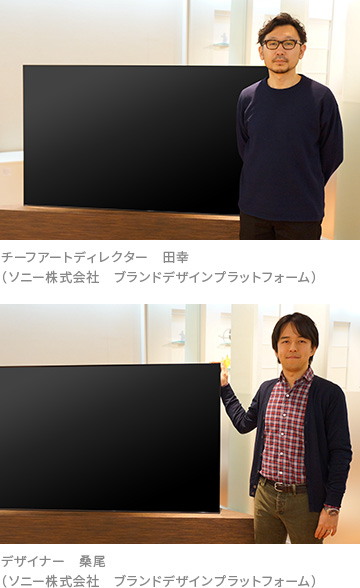
―― 『A1シリーズ』のデザインで目指したものを教えてください
<チーフアートディレクター 田幸 / デザイナー 桑尾>没入感の高い映像体験を実現するために、極限までシンプルな佇まいを目指しました。まず、すべてが入った一枚板のデザインというアイデアが最初に生まれて、その一枚板を最も自然に支える構造を考え抜いた末に、背面をもう一枚の板で支える、という今回のデザインコンセプトに辿り着きました。
一見、何でもないように見えるかもしれませんが、『A1シリーズ』で実現している、スタンドを用いずにディスプレイ部のみを接地面に直に置くという特徴的なスタイルは、技術的にもデザイン的にも非常に難易度が高いことでした。なぜならば、多くのテレビでは、テレビ本体の下部にスピーカーを配置して、接地面(テレビ台など)からの反射音をも利用して音を前に出しています。つまり、十分な音響性能を確保するために、通常はテレビ本体と接地面の間にスペースを確保しなくてはなりませんし、テレビを浮かせるためのスタンドが必要になります。この問題を解決しないことには、イメージ通りのデザインを実現することは不可能でした。
今回、有機ELパネルの特性を最大限活用した「アコースティック サーフェス」というこれまでにない高音質技術を使って、我々デザイナーが思い描いていた新しいテレビのカタチをそのままに商品化まで繋げられたことは、幸運だったと思います。他にも、新しいコンセプトのテレビを商品化するためのさまざまな課題を、開発者が一丸となって解決することで、これ以上そぎ落とすところがないくらいにシンプルなデザインに仕上がったと思っています。これによって映像への没入感を一層高めることができました。

「究極のシンプルさと美しい構造体」

―― 素材やデザインで細部にまでこだわっている点があれば教えてください
<桑尾>パネル背面もガラスで覆うことで一枚板の印象をより高めています。画面を振動させるアクチュエーターは、パネル背面に左右に2つずつ配置されているのですが、アルミ素材の一本のバーで覆ったデザインにしてあります。実は注意深く見ると、アルミのバーはガラス面から少し浮いていて、4つのアクチュエーターを想起させる円筒がガラスとアルミの間に挟み込まれているのが分かります。ガラスの映り込みと相まって軽快な印象を与えるのと同時に、技術的な象徴を造形的にも表現しています。
『BRAVIA』のロゴはこのアルミのバーの上に載せてありますが、先にダイヤカット加工をしてからアルマイトで染色することで、艶を持ちつつも落ち着きのある上質な質感に仕上げました。背面のスタンドの表面には、ガラスやアルミとコントラストをつけるために、柔らかな印象のファブリック素材を採用しています。背面のスタンドにサブウーファーが内蔵されているので、音抜けも考慮したうえで、見た目も洗練された素材を選定しています。
<音響設計 吉岡>背面のスタンドにあるサブウーファーは、音響設計としては容量を大きくとりたいという思いがありますが、一方でデザイナー目線では美しい佇まいにするために、できるだけコンパクトにしたい思いがあります。商品を作る際に社内での調整が難しいところになりますが、デザイナーが「確かにこの低音が入るとすごくいい。頑張って入れる場所を検討しないと」と言ってくれ、テレビを斜めから見てもできるだけスタンドが見えないギリギリの位置にサブウーファーのための広いスペースを取ってくれました。理想のテレビを作りあげるために、関係者が同じ方向を向いて商品づくりを行うことができたのです。

「心地よい空間体験、計算しつくされた傾きが生み出す究極の没入体験」

―― 『A1シリーズ』の没入体験の秘訣を教えてください
<田幸 / 桑尾>画面は5度傾斜しています。テレビが大画面化していることで、最近はテレビ台の高さの低いものが出てきています。そういったローボードなどを使用する時には、垂直に画面が立っているよりも、少し後ろに傾いている方がリラックスして見られると考えています。たとえば、大きい板が隙間なく接地面にドンと置いてある状態で心地よく見られるのは、絵を壁に立て掛けてあるような角度だと思います。スマートフォンや携帯電話の画面をみるときも少し斜めの方が見やすい、それと同じ考えです。スタンドのない『A1シリーズ』を見るときに、その心地よい角度がどのぐらいなのかを、検証に検証を重ねて突き詰めた結果が5度だったということです。
また、有機ELパネルは特性上、視野角のことをあまり気にする必要がありません。背面の見た目やケーブルマネジメントにもこだわったので、設置の自由度や日々の使いやすさも格段に高まりました。近年、テレビの大型化が進むにつれて、空間におけるその存在感も大きくなっています。テレビそのものの存在感を際立たせるのではなく、絵を壁に立て掛けるかのような自然な佇まいやシンプルなデザインを実現すること、リラックスできる心地よい空間体験を演出することが、ひいては視聴時の没入体験に寄与するのではないかと考えています。テレビの置く場所が変わることで、住空間やライフスタイルによりよい変化を起こすことができればと思っています。

ソニーストアで購入
KJ-65A9F65V型
ソニーストアで購入すると
KJ-55A9F55V型
ソニーストアで購入すると
KJ-77A177V型
ソニーストアで購入すると
KJ-65A8F65V型
ソニーストアで購入すると
KJ-55A8F55V型
ソニーストアで購入すると
※ 2018年12月から放送が開始される「BS・110度CSによる4K・8K衛星放送」を楽しむには、地上・BS4K・110度CS4Kチューナー『DST-SHV1』が必要です